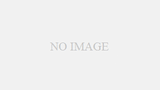このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
去る 昨年の11月25日(火)の「第六感(スピリチュアリティ[spirituality])」のブログで、「数年前(平成19年12月)、心身医学の某・医療系の学生サークルに委託されて、分科会を開催致しましたとき・・・」と記させて頂きましたように、このときを初めと致しまして、数回開かせて頂きました。 因みに、 全人SWS’08のブログも記させて頂きました。

誠に有り難いことに、上記の心身医学の某・医療系の学生サークルである「全人的医療を考える会」のS.W.S.(Summer WorkShop)の開会の挨拶を委託されました。因みに、古事記に記載されている 産巣日(結)の内容を 字に書いて 示して 話しています(平成22年8月・神奈川県川崎)

分科会の様子(平成22年8月・神奈川県川崎)
なお、これらの機会に参加者の方々、そして、去る 昨年の10月7日(火)の「ボランティア・地域医療」のブログで記させて頂きました、母校の医学部と某・看護の大学が主催しています地域医療研究会の学部生の方々に話す内容で御座います。(^O^)
すなわち、
人間科学が焦点を当てる事象は大きく2つに分けられます。
一つは、「客観的な事象」、そして、
もう一つは、「主観的・相互交流的な事象」です。
前者の「客観的な事象」は、狭義でのサイエンス(英語:science)(科学)、すなわち、五官(五つの感覚用器官)、眼・耳・鼻・舌・身によって、認知・知覚出来る範囲です。
後者の「主観的・相互交流的な事象」を扱うことは、従来、医の(medical)アート(art)として理解されていて、サイエンスの対象としては、考えられていなかったのです。
但し、医療現場で実際に起こる事柄にアプローチしようとするとき、主観的、あるいは、相互交流的な事象を避けて通ることは出来ないと言われています。
クライエントが訴える心理的pain(痛み)でも、主観的です。長時間鼾(いびき)をかいて寝ていても、眠れないとクライエントが不眠を訴えるのも主観的です。
医者の勘ということも言われています。友人との話しでは、経験からも生まれて来るということになりました。
100%の結果を見て、判断出来ればいいのですが、3割位の情報で決断しなければ間に合わないことがあると言われています。
また、人生においても、3割位の情報で決断しなければならないことがあると言われています。この自らの人生の判断の場合は、やれそうかという予感が判断に関わってくるとされています。
去る11月13日の「親の受診に付き添っていること・3」のブログのコメントの回答、すなわち、コメント2で、「『勘の研究』という著書(10数年前、当時の某・講師に勧められました。)」のことを言及致しましたが、勘に関することも書籍になっています。
研究者でもそうです。何をテーマに選ぶか、勘とかイマジネーション(imagination)(想像力)が大きなウェート(weight)を占めると言われています。
某・筑波大学名誉教授は、レニン(renin)の遺伝子解読に成功しましたが、レニンを選んだのは勘とのことでした。
多変数解析関数の分野で世界的業績をあげた、明治時代生まれの某・大数学者によりますと、抽象的に思われる数学のような分野でさえ、情緒の向く方向に数学は発展するとのことで御座います。
主観的なことが大切になって来ていますね。
さて、話しを戻しますと、前者の「客観的な事象」を対象とするのは、一般的にも馴染(なじ)みのあるE.B.M.(Evidence-based medicine )です。わかり易く申しますと、Evidenceは辞書では根拠、証拠の意味です。根拠に基づいた医療のことです。例えば、去る11月17日(月)の「黒胡麻(ごま)」のブログの中段やや下に、「夏の健康診断」のことを言及させて頂きましたが、健康診断でしたら、検査結果(根拠)を見て、総合判定するような医療です。医師になってからは、9年間、この健康診断と総合判定に携わっておりました。
後者の「主観的・相互交流的な事象」を対象とするのは、N.B.M.(Narrative-based Medicine)です。放送用語にナレーション(narration)(物語ること)という言葉がありますね。Narrativeは物語という意味です。物語に基づいた医療です。クライエントが体験し、そして、語る物語があります。
一方、心理療法では、脚本分析というのがあり、クライエントがどのような脚本を持っているか、どのようなシナリオを持っているか、これがその人の人生に重大な影響を与えるということが言われています。医療者とクライエントとの結びがあって、相互交流する中から生まれて来る、浮かび上がって来る、萌(も)え上がって来る、そして、湧き上がって来る、新しい物語を創るように目指す医療です。
このときに、古事記の物語を用いると、効果的です。一例を申しますと、社会的引き籠もり(social withdrawal)を深刻に考え過ぎている場合、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天岩戸(あまのいわと)に神隠れなされた物語を話します。人が考えることは大切なことですが、考え過ぎることには気を付けなければなりません。この話しを致しますと、誠に有り難いことに、深刻に考え過ぎていることを回避出来るようです。某・講師から子息のことを相談されたときも、また、その事例を勉強会で伝えたときにも、誠に有り難いことに、感動して頂きました。天照大御神のぉ蔭であると、去る11月03日(月)の「産土(うぶすな)の神社・参拝」のブログ、そして、去る12月04日(木)の「神社参拝」のブログで記させて頂きましたように、天照大御神をぉ祀りしている産土(うぶすな)の神社に少なくても毎月一回、参拝して参りました。
この新しい物語を創るように目指すことは、身近な所でも応用出来ます。様々な集団で仲良く交流されて、話し合って、(古来、日本では、「愛」のことを「産巣日(むすび)」と云ったのですが、)むすびの力が働いて、その集団の新しい物語を創り上げていくのと同様で御座います。
この新しい物語が、その後の個人、もしくは、集団の将来に影響を与えて参ります。勿論、その後の行動、そして、進路にも関わって来ると思われます。
精神分析(心理学)はサイエンスでは無いが、サイエンスで評価されるとされています。今後、「古事記の物語に基づいた医療」を評価することが必要になって来ると思われます。唯々感謝。(^-^)
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)