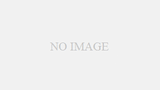このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、去る 一昨々年の12月24日(火)の「創り変える力(大和民族)」のブログを記させて頂きました。
また、去る 一昨年の6月7日(日)の「国学」のブログ そして 去る 4年前の7月19日(木)の「もののあわれ(配達員・鰻の蒲焼・157[父親の食事])」のブログのそれぞれ上段に、
「(前略)某・国立大学教授(男性)によりますと、明治時代の文学は 一言『喪失』を表現していると定義することが出来る とのことでした。一方、某・私立大学教授(男性)によりますと、日本には 西洋にない 素晴らしい文学がある とのことでした。つまり、西洋の文学が とても 行き着くことが出来ない、聖人の領域の文学が 日本には ある との旨でした。すなわち、日本の明治時代の自然主義文学 や 自然主義文学の定義者である ゾラ(仏語: Émile François Zola)の文学ではなくて、吉田 兼好の随筆『徒然草』、鴨 長明の『方丈記』 そして 俳人・松尾 芭蕉の紀行 および 俳諧 『おくのほそ道』とのことであります。 因みに、この『徒然草』、『方丈記』 そして 軍記物語『平家物語』など、仏教的無常観を抜きにして 日本の中世文学を語ることは出来ない とされています。この『無常観』は、中世以来 長い間 培ってきた 日本人の美意識の特徴の一つと言って よいであろう とのことです。更に、日本人は 春夏秋冬 すなわち 季節の移り変わり つまり 無常を 『もののあわれ』としています。誠に、日本人の凄いところの一つであると思われます。なお、これらのことは、10数年以上前、去る 4年前の12月17日(水)の『万年筆』のブログの冒頭で言及致しました友人に話しました。(後略)」と記させて頂きました。すなわち、ネガティブ(英語:negative)とも される 仏教的無常観を 日本人は、四季の移り変わりとして つまり「もののあわれ」として、恰も ポジティブ(英語:positive)に しかも プラス(英語:plus)思考で解釈されたかのように 創り変えているのであります。 因 みに、上記のように これが、誠に 日本人の凄いところの一つであると思われます。なお、この話は 去る 4月7日(木)の「保険外交員の訪問・続報3(前編)」のブログ や 去る4月7日(木)の「保険外交員の訪問・続報3(後編)」のブログなどに記させて頂きました保険外交員たち、去る 6月16日(木)の「信用金庫の営業・続報14・前編」のブログ や 去る6月16日(木)の「信用金庫の営業・続報14・後編」のブログなどに記させて頂きました 営業の方 そして 医療介護スタッフ と 介護スタッフ すなわち ケア マネージャーの方、マッサージ師の方、理学療法士の方、訪問看護師の方、介護福祉士の方 それから 家政婦たちに伝えましたら、誠に有り難いことに 頷いて 納得してくれました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)