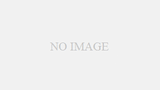このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、去る2月14日(土)の「絵本の影響」のブログ を記させて頂きましたが、絵本についてで御座います。幼い頃、アンデルセン(丁語:Hans Christian Andersen)(丁の童話作家)の創作童話である「鉛の兵隊」を読みました。最近 調べてみますと、題名が「錫の兵隊」となっている絵本の方が多いですね。去る8月30日(日)の「衝突」のブログ の中段やや下に、
「(前略) ガソリンのオクタン価を高めるために、四エチル鉛が多く添加されていたのです。(後略)」と記させて頂きました。確かに、子供のおもちゃの素材と致しましては、鉛では 危険ですね。素材が錫でしたら、比較的安全です。缶詰にも使われる ブリキの表面は、錫ですからね。因みに、 ブリキは、鉄の表面に錫を鍍しています。なお、イオン化傾向を考えますと、錫よりも鉄の方が大きい すなわち 鉄の方がイオン(英語:ion)になり易いです。よって、表面の錫が錆びることはありません。錆びると致しましたら、長期間掛けて 表面を鍍された錫に傷が入って そこから内部の鉄の方が 先に錆びます。
ガソリン(英語:gasoline)に因ませて頂きますと、中学校の体育教師は ガソリンがいい匂いだったとのことでした。子供の頃、態々 自動車のある所に行って、そのガソリンの匂いを嗅いだとのことでした。その昔は、無鉛ガソリンだったのですね。勿論 今でも、一部の発展途上国を除いて、ガソリンに鉛は添加されていないとされています。なお、日本では、世界に先駆けて 自動車用ガソリンの無鉛化が進められ、昭和61年(1986年)に 世界で初めて 自動車用ガソリンの完全無鉛化が達成されたとのことであります。
話を戻しますが、「錫の兵隊」の話の最後の方で、この兵隊は 魚に飲み込まれてしまいます。童話には、心理的なことが隠されているとされています。この魚に飲み込まれるという描写は、組織に飲み込まれ、没個性化されてしまう phobia(英語)(ネガティブ[英語:negative]で御座いますし、お読み下さっている方々に影響を お与えすることの無いように、日本語で綴ることを控えさせて頂きましたが、以前、それではわからない、と指摘を頂きましたので、日本語も併記させて頂きます。小さく記させて頂きます。恐怖のことで御座います。以下、phobiaと記させて頂きます)を表しているのかもしれません。だから、アンデルセンは、生涯に亘り 各地を旅して過ごしていたのかもしれません。日本では、江戸時代の 曹洞宗の禅僧である良寛さんも、生涯に亘り 各地を旅しましたね。寺の住職となることをよしとせず、いかなる組織にも所属しなかったとのことです。去る1月1日(木)の「謹んで新年の御祝詞を申し上げます。(^O^)」のブログ のコメント1の回答、すなわち、コメント2に、
「(前略)『良寛(和尚)』と お伺い致し、去る平成9年、母親に依頼されて 映画『良寛』を観に行ったことが御座いました。御承知のように、新潟県出雲崎に記念館がありますね。(後略)」と記させて頂きました。新潟県中越に、良寛記念館があります。十数年前 すなわち 平成9年夏、母親に誘われて 映画「良寛」を観に行きました。但し、数日前、母親に このことを話しても もう覚えていませんでした。因みに、昨日 すなわち 12月5日(土)の「霊峰・富士・8(榊 と 仏花)」のブログ の上段に、
「(前略)母親によりますと、父親は 昔から 心配性です。(後略)」と記させて頂きました。母親によりますと、父親には 昔から phobiaもあるとのことでした。phobiaから、心配性になっているのですね。なお、前述のアンデルセンは 極度の心配性であったらしく、外出時は非常時に建物の窓からすぐに逃げ出せるように 必ずロープ(英語:rope)を持ち歩いたそうです。さらに、眠っている間に死んだと勘違いされて、埋葬されてしまった男の噂話を聞いて以来、眠るときは 枕元に「死んでいません」という書置きを残していたとのことです。70歳の生涯でした。上記の良寛さんは、74歳の生涯でした。良寛さんと云えば、多くの方々は 子供達と一緒に手毬をつき乍ら遊ぶ 温厚な老僧の姿を思い浮かべられることでしょう。しかも、多くの和歌 そして 漢詩を残しています。なお、去る10月5日(日)の「ボランティア・高尾山登山」のブログ と 去る1月21日(水)の「ボランティア・高尾山登山・その2」のブログ で、
「(前略)18年間、月二回、日曜日に、・・・ボランティアを、このトップの方々二人に委託されて、行って参りました。そのボランティアで、過日、子供達と父兄を連れて・・・(後略)」と お伝え申し上げました。このボランティアでは、子供達と交流するときに いつも良寛さんのように と思って 臨んでいました。また、このボランティアの野外研修のときには、必ず 和歌作りをしていました。
ときに、昨日、一日のおかず(菜食)は、
まず、ひじき、人参、椎茸、豆腐 そして お揚げの白和えです。因みに、ひじきには、去る11月12日(水) の「ひじき」のブログ で お伝え申し上げましたように、鉄分(化学式:Fe)、カルシウム(化学式:Ca)、そして、マグネシウム(化学式:Mg)が含まれています。また、去る 昨年の11月24日(月)の「抗酸化物質」のブログで、「(前略)人参は皮を剝かないで調理するとのことでした。(後略)」と記させて頂きました。このことにつきまして、去る7月12日(日)の「柴漬け」のブログ の中段やや上に、
「(前略)去る6月29日(月)の『微笑み』のブログ のコメント1で、誠に有り難いことに、(中略)御賛同頂きました。(後略)」と記させて頂きました。
および、去る4月8日(水)の「南瓜」のブログ の中段やや下に、
「(前略)奈良時代、遣唐使が中国から豆腐の作り方を日本に持ち帰ったということが豆腐伝来説として有力とされています。その伝来した際、豆腐と納豆の名称が逆になって伝わったとのことです。考えてみますと、納豆の製法である『豆を(納豆菌で)腐らす』のは正しく納豆であり、豆腐の製法である『豆を(型に)納める』のは正しく豆腐でありますね。(後略)」と記させて頂きました。
なお、豆腐の白和えにつきましては、去る4月10日(金)の「豆腐の和えもの」のブログ そして 去る2月7日(土)の「白和え」のブログ でも記させて頂きました。

豆腐の白和え
そして、厚揚げの煮物です。因みに、 この上に 去る11月25日(水)の「山椒」のブログ の中段に記させて頂きましたように 山椒の粉を掛けてみました。

厚揚げの煮物
また、人参、椎茸、いんげん、大豆 そして お揚げの煮物です。因みに、椎茸のことは、去る6月12日(金)の「レタス」のブログ の中段やや上に記させて頂きました。および、去る 昨年の11月17日【月】の「黒胡麻」のブログ でも お伝え申し上げましたように、隠元禅師がいんげん豆をもたらしたとされています。
ならびに、去る 昨年の11月6日(木)の「イソフラボン」のブログ で お伝え申し上げましたように、枝豆(大豆)にはイソフラボン(フラボノイド[英語:flavonoid][よく御承知のポリ・フェノール【英語:polyphenol】【抗酸化物質】と呼ばれる、より大きな化合物のグループの仲間]の一種)が含まれています。なお、枝豆(大豆)に含まれています、このイソフラボン(英語:isoflavone)、レシチン(英語:lecithin) そして サポニン (英語:saponin)につきましては、去る10月10日(土)の「心身一如」のブログの中段やや上に記させて頂きました。

煮物
および、人参、豆腐、玉葱 そして しらたき(関東では「しらたき」、関西では「糸こんにゃく」と呼ばれているそうです。)の煮物です。因みに、玉葱の調理法につきましては、去る3月25日(水)の「玉葱」のブログ の中段やや下に記させて頂きました。なお、フィト・ケミカル(英語: phytochemical)であるポリ・フェノール(英語:polyphenol)(抗酸化物質)の代表と言われる程 最も種類が多いフラボノイド(英語:flavonoid)類の仲間であるフラボノール(英語:flavonol)類の一種であるクェルセチン(英語: quercetin)が、玉葱に含まれています。このクェルセチンのことは、去る10月11日(日)の「人類に有用な天然の物質」のブログ に記させて頂きました。そのうえ、そのフィト・ケミカルにつきましては、同じく 去る10月11日(日)の「人類に有用な天然の物質」のブログ 、去る10月12日(月)の「産土の神社の『例大祭』」のブログ 、そして、去る10月18日(日)の「フィト・ケミカル」のブログ のそれぞれ中段以降に記させて頂きました。それから、前述の 去る 昨年の11月24日(月)の「抗酸化物質」のブログ に、様々な抗酸化物質を記させて頂きました。
ならびに、こんにゃく(こんにゃく芋)につきましては、去る 昨年の11月16日(日)の「根菜」 そして 去る 昨年の10月16日(木)の「身土不二(今日のおかず)」のブログ で記させて頂きました。

煮物
最後に、昆布と椎茸のダシによります、茄子 そして 葱の味噌汁です。この味噌汁に、前述の 去る11月25日(水)の「山椒」のブログ の上段に記させて頂きました 山椒の粉を掛けてみました。なお、去る 昨年の12月17日(水)の「万年筆」のブログ の冒頭で言及致しました友人が 自宅に見えたときにも、味噌汁に この山椒の粉を勧めたことがあります。数年前のことであります。因みに、昆布のことは、去る 昨年の10月24日(金)の「健やかに生活をして頂くために(今日のおかず)」のブログ の中段に記させて頂きました。また、去る3月22日(日)の「わかめ」のブログ の中段に、
「(前略) 昆布やわかめなどの海藻類には、『水溶性食物繊維』であるヘミセルロースが含まれています。(後略)」と記させて頂きまして、食物繊維につきまして お伝えさせて頂きました。更に、食物繊維のことは、去る 昨年の11月20日(木)の「切り干し大根(昨日のおかず)」のブログ の中段でも記させて頂きました。
および、去る4月19日(日)の「なすび」のブログ の中段に、
「(前略)去る3月24日(火)の『茄子の違い』のブログ の中段に、茄子の話を記させて頂きました。そして、去る4月1日(水)の『アントシアニン』のブログ に、茄子にはアントシアニンが含まれていると記させて頂きました。しかも、去る4月17日(金)の『炒り煮』のブログ の中段に、『(前略)茄子は皮を剝かないで調理するとのことです。こうすれば、茄子の皮に含まれているアントシアニンというポリ・フェノール(抗酸化物質)を摂取ることが出来ますね。(後略)』と記させて頂きました。そのうえ、去る1月1日(木)の『謹んで新年の御祝詞を申し上げます。(^O^)』のブログ の上段やや下に、・・・(後略)」と記させて頂きました。
それから、去る 昨年の10月9日(木)の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から大乗へ」のブログ の中段に詳細に記させて頂きましたように、葱にはアリシン(硫化アリル)(英語:allicin)が含まれています。
ところで、昔から言われている味噌汁のことを発展させた話につきましては、去る4月8日(水)の「南瓜」のブログ の中段以降に記させて頂きました。おまけに、去る7月11日(土)の「日本人の魂の食べ物」のブログ の中段やや下に、
「(前略)去る6月29日(月)の『微笑み』のブログ の中段やや下に、『味噌汁は、日本人の魂の食べ物ですね。』と記させて頂きました。(後略)」と記させて頂きました。加うるに、去る8月23日(日)の「アスコルビナーゼ」のブログ の下段やや上に、味噌汁である「御御御付」のことにつきまして、
「(前略)『御』が3つも付くのですから、誠に有り難い食べ物ですね。(後略)」と記させて頂きました。

味噌汁
同居している両親は、と以前 訊かれましたので、お伝え申し上げましたが、両親は何でも食べます。
前述の 去る昨年の10月9日(木)の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から大乗へ」のブログ に記させて頂きました過程があり、誠に有り難いことに、母親の理解を得て、菜食にさせて頂いております。
あと、これらのおかずに、玄米御飯で御座います。玄米も、庶民的にスーパー・マーケットで購入して来ます。
御承知のように、玄米の糠には、去る 昨年の11月10日(月)の「らっきょう(昨日のおかず)」のブログ で お伝え申し上げましたように、糖質からエネルギーをつくり出すときに役立つとされているビタミンB1(英語:thiamin)が含まれています。ビタミンB1(チアミン)のことは、去る3月30日(月)の「脳の神経細胞の新生」のブログ の上段から中段に掛けてでも記させて頂きました。
また、らっきょうには、キャベツの約50倍の、前述の「水溶性食物繊維」が含まれています。キャベツのことは、去る12月20日(土)の「キャベツ」のブログ に記させて頂きました。更に、らっきょうには、ビタミンB1の吸収を助ける、「アリシン(硫化アリル)(英語:allicin)」という成分が多く含まれています。因みに、「アリシン(硫化アリル)」は、葱類に共通して含まれています。玉葱に含まれている、血液をサラサラにする効能があるとされる「アリシン(硫化アリル)」を効果的に摂取るための調理法は、前述の 去る3月25日(水)の「玉葱」のブログ に記させて頂きました。なお、玉葱に多く含まれるフラボノールにも、血液をサラサラにする働きがあるとされています。このフラボノールは、前述のフラボノイド類の仲間であり、上記のフィト・ケミカルであります。
それから、玄米には、ビタミンE、食物繊維、そして、K(カリウム)が含まれています。因みに、K(カリウム)のことは、去る1月9日(金)の「茄子」のブログ に記させて頂きました。また、玄米のような穀類に含まれている食物繊維は、「不溶性食物繊維」です。前述の「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」のことにつきましては、前述の 去る3月22日(日)の「わかめ」のブログ の中段に記させて頂きました。
なお、去る11月20日(金)の「仏花(菊の花)」のブログ の下段に、「古事記」と「日本書紀」を引用させて頂いて、日本人の主食である お米は 誠に有り難い という話を記させて頂きました。

玄米御飯
玄米の食べ方につきましては、前述の 去る 昨年の11月17日(月)の「黒胡麻」のブログ で記させて頂きました。また、玄米の炊き方につきましては、去る 昨年の11月26日(水)の「蕗」のブログに記させて頂きました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)