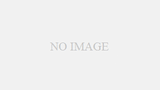このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、昨日、一日のおかずは、
まず、市販の納豆です。因(ちな)みに、母校の、某・理事長に勧められた内科学教室に入局した平成3年から10数年間、日本神経学会と日本内科学会、同じく平成3年から数年間、日本動脈硬化学会と日本老年医学会、そして、母校の、当時の同・内科学教室助教授(当時の名称・現在の名称は准教授)に勧められて、平成9年から10数年間、日本未病システム学会の学会員でありました。御承知のように、納豆には、血栓溶解を促す成分である「ナットウキナーゼ(酵素)」が含まれています。血栓を溶解する医薬品としてウロキナーゼが知られていますが、「ナットウキナーゼ」の血栓溶解作用が持続する時間は8~10時間といわれ、ウロキナーゼの持続時間よりも長いとされています。しかも、「ナットウキナーゼ」は天然由来の成分でありますから、大豆アレルギーがなければ、まず、副作用の心配はありません。夜食に納豆を召し上がって頂きますと、睡眠中、cerebral infarction(英語)(ネガティブ[negative]で御座いますし、お読み下さっている方々[かたがた]に影響をぉ与えすることの無いように、日本語で綴[つづ]ることを控えさせて頂きましたが、以前、それではわからない、と指摘を頂きましたので、日本語も併記させて頂きます。小さく記させて頂きます。脳梗塞のことで御座います。)の予防効果があるとされています。両親、特に母親によりますと、夜食に1パックの納豆は食べられないとのことで御座いますので、半パックの納豆を勧めています。
一方、納豆には、血液凝固を促進する「ビタミンK2」も含まれています。但し、「ビタミンK2」は、直接血を固(かた)めるわけではありません。「補酵素」と呼ばれ、血液を固(かた)めるために、肝臓で血液凝固因子が生成することを助ける働きがありますが、「補酵素」には他にも種類があり、「ビタミンK2」が含まれているからといって直(ただ)ちに血液が固まり易くなるというわけではありません。
人間の身体には血栓を作る働きと、溶かす働きが両方備わっていて、常に両方を行うことでバランスを取っています。「ナットウキナーゼ」は血栓を溶かす働きを補うことが出来るとされています。だからといって「ナットウキナーゼ」が多いと血が止まらない、ということはなく、そのときは血液を固(かた)める働きの方(ほう)が作用してバランスを取っていると考えられるとのことで御座います。
因(ちな)みに、御承知のように、人間の身体には骨をつくる造骨細胞と骨をこわす破骨細胞、すなわち、両方の働きが備わっていて、新陳代謝が行われています。全部の骨を含めて新陳代謝が行われる時間は、約16年と言われています。
去る10月15日(水) の『りんごの効用 』のブログ の中段に、
「(前略)医食同源、そして、薬食同源と云われますが、食物はぉ薬であり、特に、生でまるごと食べるりんご(前述のように、すりおろしりんごはいいです。)はぉ薬であると思います。当たり前の食品の中にも、誠に有り難い食べ物が御座います。(後略)」と記させて頂きました。納豆もぉ薬のような、誠に有り難い食べ物であると思われます。しかも、庶民にとりまして、経済的な食品です。誠に有り難いことに、神様は、高価なものでなくとも、庶民にとりまして入手し易い、同様に効果のあるものを用意して下さっているように思われます。
ときに、去る10月21日(火)の「バランス良くまるごと」のブログ に記させて頂きましたように、納豆は、大豆を丸(まる)ごと食べることが出来る食品であるということで御座います。また、納豆は、発酵食品であります。すなわち、納豆菌が繁殖発酵しますと、食べ易く消化吸収され易くなると言われています。
また、去る11月06日(木)の「イソフラボン」のブログ でぉ伝え申し上げましたように、大豆にはイソフラボン(フラボノイド[よく御承知のポリフェノールと呼ばれる、より大きな化合物のグループの仲間。]の一種)が含まれています。かつてはよく、イソフラボンにはエストロゲン(女性ホルモン)様の作用がある、と言われ、植物性エストロゲンと呼ばれてきました。

納豆
また、さつま芋、そして、南瓜(かぼちゃ)です。因(ちな)みに、さつま芋のことは、去る10月16日(木) の「身土不二」のブログ に記させて頂きました。

さつま芋、そして、南瓜(かぼちゃ)
そして、市販の、赤蕪(あかかぶ)の酢漬けです。この中から少しです。因(ちな)みに、一昨日、すなわち、去る3月14日(土)の「食塩を控えて、尚且(なおか)つ美味(おい)しく食べる工夫(食事療法)」のブログ の下段に、
「(前略)このコメント2で、上記の11.の項目に関しまして、『少塩多酢』、そして、前述の『お酢も【百薬の長】』とのことに、触れさせて頂きました。(後略)」と記させて頂きました。

赤蕪(あかかぶ)の酢漬け
それから、トマト(強力な抗酸化物質であるリコピンが含まれています)、ピーマン、玉葱(たまねぎ)、そして、ぶなしめじのスパゲッティです。因(ちな)みに、抗酸化物質のことは、去る11月24日(月)の「抗酸化物質」のブログ で記させて頂きました。また、「ぶな」のことは、去る12月26日(金)の「ぶなしめじ」のブログ に記させて頂きました。

スパゲッティ
最後に、昆布(こんぶ)と椎茸(しいたけ)のダシによります、茄子(なす)、そして、葱(ねぎ)の味噌汁です。因(ちな)みに、昆布(こんぶ)のことは、去る10月24日(金)の「健(すこ)やかに生活をして頂くために」のブログ に記させて頂きました。また、去る10月09日(木)の「笑いと菜食療法ー菜食に導かれた過程ー小乗(しょうじょう)から大乗(だいじょう)へ」のブログ の中段に詳細に記させて頂きましたように、葱(ねぎ)にはアリシン(硫化アリル)(allicin)が含まれています。

味噌汁
同居している両親は、と以前、訊(き)かれましたので、お伝え申し上げましたが、両親は何でも食べます。
前述の、去る10月9日(木)の「笑いと菜食療法ー菜食に導かれた過程ー小乗(しょうじょう)から大乗(だいじょう)へ」のブログ に記させて頂きました過程があり、誠に有り難いことに、母親の理解を得て、菜食にさせて頂いております。
あと、これらのおかずに、玄米御飯で御座います。玄米も、庶民的にスーパー・マーケットで購入して来ます。
御承知のように、玄米の糠(ぬか)には、去る11月10日(月)の「らっきょう」のブログ でぉ伝え申し上げましたように、糖質からエネルギーをつくり出すときに役立つとされているビタミンB1(チアミン)が含まれています。また、らっきょうにも、ビタミンB1の吸収を助ける、前述の「アリシン(硫化アリル)(allicin)」という成分が多く含まれています。
更に、玄米には、ビタミンE、食物繊維、そして、K(カリウム)が含まれています。因(ちな)みに、K(カリウム)のことは、去る1月9日(金)の「茄子(なす)」のブログ に記させて頂きました。

玄米御飯
玄米の食べ方(かた)につきましては、去る11月17日(月)の「黒胡麻(ごま)」のブログ で記させて頂きました。また、玄米の炊(た)き方(かた)につきましては、去る11月26日(水)の「フキ(蕗)」のブログ に記させて頂きました。唯々感謝。(^-^)
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)