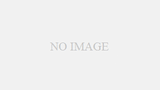このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、去る 一昨年の10月9日(木)の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から大乗へ」のブログ の上段に、
「(前略) ターミナル・ケア(英語:terminal care)(終末期介護)の必要な患者さんでありました。(後略)」と記させて頂きました。
一方、去る 一昨年の11月25日(火)の「第六感(スピリチュアリティ[spirituality])」のブログ そして 去る 一昨年の10月6日(月)の「アゲハ蝶(スピリチュアリティ[spirituality])」のブログ などで、スピリチュアリティ(英語:spirituality)のことを記させて頂きました。
前述のターミナル・ケアの必要な患者さんを担当させて頂いた頃から、ターミナル・ケアに スピリチュアリティを取り入れることが大切であると思われるようになりました。仏教的には、輪廻(梵語:संसार saṃsāra、英語:reincarnation)があるということであります。すなわち、この世(此岸)の終わりで 全てが終わるのではなくて、あの世(彼岸)があるということで御座います。更に 云えば、生命は 行き通している ということであります。この世(此岸)を去ることは、あの世(彼岸)の誕生ということであります。因みに、幼少の頃に聞かされたことで、天体の寿命は 数十億年以上であるのに、何故 尊厳のある人間の寿命は それに比べて 遥かに短いのであるかということであります。人間も、天体同様に、行き通すことによって それに匹敵する寿命を有しているのではないか ということで御座います。
ときに、去る 一昨年の10月7日(火)の「ボランティア・地域医療」のブログ 、去る1月25日(日)の「ボランティア・地域医療・その2」のブログ 、去る1月29日(木)の「ボランティア・地域医療・その3」のブログ そして 去る8月8日(土)の「ボランティア・地域医療・その4」のブログ に、
「(前略) 先輩から委託されて学部生であった頃から関わっております、母校の医学部と某・看護の大学が主催しています地域医療研究会(後略)」と記させて頂きました地域医療研究会の某・看護の学部生の方から、去る平成19年9月14日(金)に 以下のようなメール(英語:mail)を頂きました。すなわち、「(前略) 論文も昨日担当教員と面談して、少しずつ進めているところです。先方との話が上手くまとまれば、当初やりたかったホスピスでの実習で論文を書けそうなので、よりやる気がわいてきました。倫理的に終末期患者様を研究対象にするのは難しいと聞いていましたので、諦めていたのですが、幸運な便りが舞い込みかけています。(原文通り)(後略)」とのことでありました。そこで、
「(前略)基本的に 基教が思想の根底にある欧米で、告知の際に キューブラー=ロス(独語:Elisabeth Kübler-Ross)の受容に至る五段階は、御承知のことで御座いましょう。御承知のように、キューブラー=ロスの著書である『死ぬ瞬間』によりますと、五段階の『死へのプロセス』があるとのことです。すなわち、『否認』、『怒り』、『取引』、『抑うつ』 そして 『受容』です。御承知のことであらせられると存じますので、以上の五段階のそれぞれにつきましての説明は割愛させて頂きます。更に、アルフォンス・デーケン(独語:Alfons Deeken)神父によって、『期待と希望』という第六の段階が示されています。(後略)」と返信致しました。但し、去る 一昨年の10月12日(日)の「薔薇の花」のブログ の最後に、
「(前略)平成20年の夏と22年の夏に、心身医学の某・医療系の学生サークルから、委託されて、分科会を開きましたとき、参加してくれた、臨床心理士志望の男性から、
『あの日に前々から疑問に思っていたのに言えなかったことがありまして、地域医療研究会の卒業生の方とは卒後連絡を取らないのがけじめであると以前メールで書かれてありましたが、そこまでストイックにおなりにならなくてもと考えたのですが、どんなところでしょうか?もちろん先生の事ですから、深遠なるお考えがおありになっての事でありましょうが・・・何故か疑問でした。』とのことで御座いました(地域医療研究会の卒業生とは、卒後、こちらから連絡をとったことは御座いません。(^O^)それが、けじめであると思っております、と伝えましたことに関してで御座います)ので、回答致しました。
すなわち、
卒業生の方々は、その後就職して、スタッフでは御座いませんので、連絡する公的目的が無いと存じますので、当たり前のことであるか、と存じます。
それでも、連絡すると致しますと、当方は未婚で御座いますので、特に、相手が独身女性で御座いますと、誤解されることになるか、と存じます。
御承知のことであらせられますように、諺で、『李下に冠を正さず』、そして、『瓜田に履を納れず(瓜田に靴を直さず)』と申しますが、当方は、歓送迎会で挨拶を委託されますし、過去に、推薦文を求められた者で御座いますから、誤解される真似を致しますのも、会の為に控えなければなりません、との旨の内容を回答致しました。
前述の分科会(この方は男性2人で参加してくれました)参加者である、もう一人の、この方の友達の男性にも、連絡がありましたときに、返信で伝えましたら、誠に有り難いことに、納得してくれました。唯々感謝。(^O^)(後略)」と記させて頂きました。上記のように、その地域医療研究会の卒業生とは、卒後、こちらから連絡を取ったことは御座いませんし、その後の交流も御座いません。
因みに、 去る12月10日(木)の「クリーニング」のブログ の上段やや下に、転移(英語:transference)(精神分析用語)を言及させて頂きました。前述のように 学部生から この転移を受けましたら、これを 如何に建設的な方向に向けるか、更に より多くの人々の福祉の為になるか ということに繋がるように と心掛けております。このことは、真剣さを要求されます。しかも、前述の、去る1月25日(日)の「ボランティア・地域医療・その2」のブログ の上段に、
「(前略) (この)地域医療研究会の追いコン(送別会)に呼ばれまして、話すことを依頼されると、申していることの話の触りを記させて頂きます。(^O^)
まず、去る(昨年の)1月7日(水)の『受験のアドバイス』のブログ の下段にも記させて頂きましたように、
どうぞ、4月からの御自分の お姿をイメージして下さい。イメージには、具象力、すなわち、実現する力がありますから、今迄、経験したことを生かすことが出来て、医師として、看護師として、保健師として、そして、その他の分野に進む方もおられるかもしれませんが、その真価が十二分に発揮されますように心より祈っております。(中略)
兎も角、若い力は素晴らしい。こういう若い力を評価してくれる、しかも、人間性の優れた、皆さんにとって尊敬できる、そういうトップ(英語:top)のもとに付かれて、励まれますことを心より願っています。(中略)
一人が現われると、『観』、すなわち、見方が変わります。そして、周囲に影響を及ぼします。皆さんに心より期待致しております。御活躍なされますことを心より祈念申します。
以上が前述致しました、話の触りで御座います。(後略)」と記させて頂きました。学部生の方々に、このように話しています。すなわち、前述の転移を受けましたら これらの若い学部生の方々が よりよい進路を選ぶことが出来ますようにと 心より祈り乍ら、話を伝えさせて頂いております。なお、機会がありまして 宜敷ければ、この転移のことにつきまして記させて頂きます。
ところで、話を戻しますと、前述の 去る 一昨年の11月25日(火)の「第六感(スピリチュアリティ[spirituality])」のブログで、「数年前(平成19年12月)、心身医学の某・医療系の学生サークルに委託されて、分科会を開催致しましたとき・・・」と記させて頂きましたように、このときを初めと致しまして、数回開かせて頂きました。これらの機会に 参加者の方々に、前述のように ターミナル・ケアに スピリチュアリティを取り入れることを話しました。すると、参加者の某・看護大学4回生の方から、去る平成19年9月19日(水)に、以下のようなメールを頂きました。「(前略)私も(前述の某・看護の学部生と同様に)教員に相談しながら文献での研究を進めています。日本人に『死を看取る』、『死に逝く人を看病する』という概念がどのようにして生まれ、それはどのような思想が元になっているのかを研究し、『看取り』に関する歴史的文化的背景について明らかにしたいと思っています。これからの『看取り』をどのように行っていくのか、どのように研究していくのかは、日本人がたどってきた歴史的文化的背景を考慮していく必要があると考えています。今は、近代社会史の本や人類史の本などを読んでいるところです。いろいろ興味深いことが書かれてあり、おもしろくなってきたところです。
私は終末期医療でも特に在宅ターミナル・ケアに興味があり、7月は2週間、訪問看護ステーションで個人的な実習をしました。全て末期がんの患者の家に訪問し、いろいろな事を学んできました。実習中に3名の方を看取り、とても貴重な経験となりました。在宅での看取りはまだまだたくさんの課題がありますが、その分、 可能性もたくさんあり、私はおもしろいと感じています。(原文通り)(後略)」とのことでありました。そこで、以下のように 返信致しました。すなわち、
「(前略)学部生のとき 神経科助教授(当時の名称・現在では、准教授ですね)との話があり、それ以来 日本の医療を探求致しております。日本人の『看取り』を どのように行っていくのか という着眼点は、医療と看護の それぞれの立場こそあるものの共通であります。(中略)
未来を見据えておられて、誠に素晴らしいですね。終末期医療とスピリチュアリティと致しまして、キーワードとして、(前述致しました)『輪廻』の話を、あの短い時間の中(前述の会のこと)で、話すことが出来、両者間で共感することが出来たので、誠に有り難く存じます。(中略)
貴重な御体験をなされ、誠に素晴らしいですね。同じく、別送で、『在宅医療』についての記事を御送りさせて頂きます。(中略)
関東に在宅訪問医療のシステム(英語:system)で 某・システムがあり、学部生の頃、主宰者 と 看護師さんと共に 在宅訪問したことがあります。今でも、大学の無医村医療の研究会にも携わっていて、今年の夏もフィールド(英語:field)に行って来ました。(後略)」で御座います。勿論 この某・看護大学4回生の方とも、卒後 こちらから連絡を取ったことは御座いませんし、その後の交流も御座いません。因みに、去る 一昨年の11月17日(月)の「黒胡麻」のブログ の中段に、
「(前略)去る(一昨年の)10月7日(火)の『ボランティア・地域医療』のブログで記させて頂きました地域医療研究会で、学部生の頃から、埼玉県神泉村(当時・無医村)(ここのフィールド[英語:field]は約四半世紀続きました)に伺っておりまして、医師になってからは、9年間伺っておりました。夏の健康診断は3日間ありますので、4泊5日になることがあり、その間の食事となる玄米を 酢でしめて持って行きます。(後略)」と記させて頂きました。また、前述致しましたように 学部生の頃 前述の某・システムで 主宰者 と 看護師さんと共に 在宅訪問した写真を 下に掲載させて頂きます。約30年前の写真です。因みに、介護保険制度は 約22年前 すなわち 平成12年(2000年)4月から 始まった 市区町村が運営する制度であります。なお、その制度が出来る前のことであります。

主宰者と共に、介護の お宅に

看護師さんと共に、介護の お宅に
および、上記の「輪廻」のことを 前述致しました分科会関係の方にも話しました。すると、その中に 「輪廻」のことを 人が死んだ後 その人のことが記憶に残る という形で この「輪廻」を捉えている学部生がいました。また、去る 一昨年の10月8日(水)の「親の受診に付き添っていること・1」のブログ また 去る 一昨年の11月9日(日)の「親の受診に付き添っていること ・2」のブログ のそれぞれ 共に中段やや上 そして 去る 昨年の2月23日(月)の「天皇陛下行幸の君恩に浴して」のブログ の中段やや下に記させて頂きました某・ボランティア(英語:volunteer)のサークル(英語:circle)の方は、この「輪廻」で説明した方が説明し易いとのことでありました。このような観点から 「輪廻」を捉えている方もいるのか と思いました。更に、この「輪廻」に因みましたことは、一昨々日 すなわち 1月6日(水)の「後生の一大事 」のブログ の中段に、「三時業」のことを記させて頂きました。しかも、終末期医療とスピリチュアリティにつきましては、仏教関係でも セミナー(英語:seminar)が行われているようで御座います。前述の地域医療研究会の某・看護の学部生の方が参加しているとのことでありました。
なお、このブログ記事の中段に、「『観』、すなわち、見方が変わる」と、「観」の転換(英語:conversion)のことを記させて頂きました。前述させて頂きました 数回開かせて頂きました分科会の中でも、繰り返し 「観」の転換のことを伝えました。また、このブログ記事の上段に、「この世(此岸)を去ることは、あの世(彼岸)の誕生ということであります。」と記させて頂きました。すなわち、ターミナル・ケア(終末期医療、終末期看護)の「観」の転換を行えば、あの世(彼岸)の産科として 明るく考えることが出来るかもしれません。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)