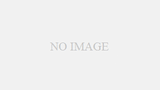このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、昨日 すなわち 8月10日(月)の「接ぎ木(昨日のおかず)」のブログ で、接ぎ木のことを記させて頂きました。接ぎ木とは、2個以上の植物体を、人為的に作った切断面で接着して、1つの個体とすることであります。このとき、上部にする植物体を穂木、下部にする植物体を台木と言います。心理療法でも、この接ぎ木のたとえがあります。
すなわち、接ぎ木をして、接ぎ木の癒合がうまくいったのかどうか、一度接いだ穂木を取って、接ぎ木の切り口を何度も確認したら接ぎ木はうまくいかないでありましょう。
また、同様のたとえとして、蒔いた種のたとえがあります。すなわち、種を蒔いて、種の芽が生えたのかどうか、一度蒔いた種を掘り返して何度も確認したら、芽がつかず、うまくいかないでありましょう。
以上の2つのたとえがあります。
ときに、御承知のように、「果報は寝て待て」という故事があります。この教えは、仏教の教義と人生の知恵を合体して出来たようで御座います。一般的に、「因果応報」ということは、柔らかく説明させて頂きますと、人はよい行いをすればよい報いがあり、そうでない行いをすればそうでない報いがあるということです。更に、「果報」を正確に言いますと、「果」の方は、善いことを行ったときによい結果が出るというように、因果が正しく廻って来ることですが、「報」の方は行為の結果がその原因通りにならないような報いのことであるとされています。何れの結果が出るにしろ、「寝て待つより方法がないのだ‥‥」と開きなおった姿勢を教えている内容です。
24年前、すなわち、十二支で二周して、今年と同じ未年のことです。医師国家試験直前に、教室で、男子学生が、この「果報は寝て待て」と話していました。すると、それを聞いた女子学生が、それじゃダメだよと言っていました。良い結果を得るためには寝て待っていたのではダメで、勉強し、働き、動き回っていないと成果が上がらないというのが、普通の意識(常識)です。
一方、日本人は働き好きで勤勉という世界的な評価を受けており、ときには働き過ぎることが、批判されています。また、去る 昨年の11月23日(日)の「アロマ・テラピー」のブログ の冒頭、そして、去る 昨年の10月18日(土)の「心身医学会」のブログ で記させて頂きましたように、約23年前に、編者から依頼されて、「心身医学を学ぶ人のために」の一部、すなわち、用語解説を執筆させて頂きました。この用語解説の203頁に、ワーカ・ホリック(英語:workaholic)のことが書かれてあります。ワーク(英語:work)とアルコホリック(英語:alcoholic)の合成語です。簡潔に お伝え申し上げますと、仕事をすることが人生そのものになってしまった働き過ぎの人、および、その状態をいいます。仕事中毒、そして、仕事依存であります。自分が働き過ぎているという自覚が無いか、乏しいとのことです。去る 昨年の10月8日(水)の「親の受診に付き添っていること・1」のブログ 、そして、去る 昨年の11月9日(日)の「親の受診に付き添っていること ・2」のブログ のそれぞれ共に中段やや上、そのうえ、去る2月23日(月)の「天皇陛下行幸の君恩に浴して」のブログ の中段に記させて頂きました某・ボランティアのサークル関係の方々の中で、常に人生を走り続けているように傍から見える先輩がいました。
この書の表紙を、再度、下に掲載致します。因みに、この書を相当数、すなわち、数10冊以上、自費で購入し、寄贈させて頂きました。心理療法内科の学会のときに、このことを編者に話しましたら、誠に有り難いことに、感謝して頂きました。なお、前述の、去る 昨年の10月18日(土)の「心身医学会」のブログ の上段に、
「(前略)元・心理療法内科の学会の理事長に依頼されて、某・日本医療心理学院で、早稲田大学やお茶の水女子大学の心理の大学院生に心身医学の講義を行っていました(後略)」と記させて頂きました。ここの臨床心理士によりますと、この書を出版社から直接買えばよかったのにとのことで御座いました。
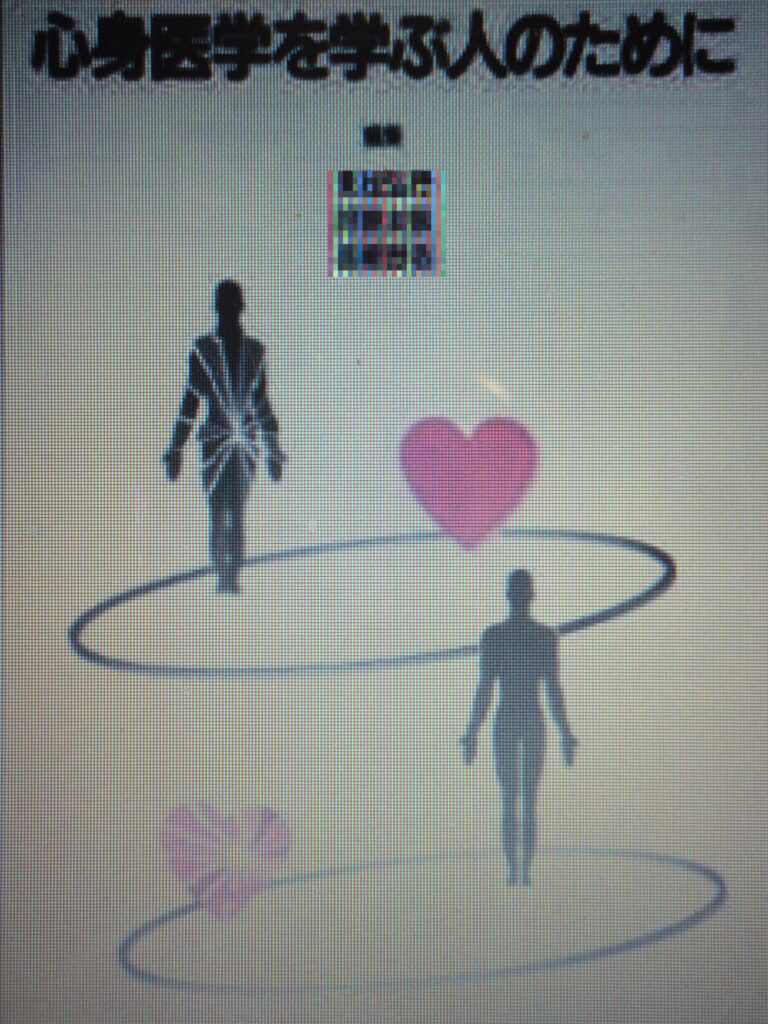
再掲・心身医学を学ぶ人のために
但し、人間が怠け者であるより、働き者である方がよいことは当然のことであって、外国の人が批判したからといって、働き者であることを否定したり恥ずかしがったりする必要はない と思われます。しかも、ワーカ・ホリックという言葉も、昭和46年(1771年)に米国の某・作家によって出版された著書の中で初めて使われました。
上記の故事の本来の意味は、「寝て待て」といっても、怠けていれば良いという意ではなく、人事を尽くした後は気長に良い知らせを待つしかないということで御座います。御承知のように、「人事を尽くして天命を待つ」という故事もあります。
前述の2つのたとえのように確認しないでは気が済まないときには、これらの2つの故事を思い出してみては如何か、と思われましたので言及させて頂きました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)