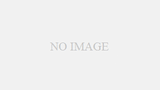このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。
リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)
さて、昨日 すなわち 10月10日(土)の「心身一如」のブログ の上段に、
「(前略)このスルフォラファンは、フィト・ケミカル(英語: phytochemical)、すなわち、植物中に存在する天然の化学物質の一種です。(後略)」と記させて頂きました。なお、“phyto”とは、ギリシャ語で「植物」という意味です。植物には、様々な栄養成分が詰まっていますが、中でも植物が作り出す自己防衛成分のことを指しています。
人に欠かせない炭水化物、蛋白質、脂質、ビタミン(英語:vitamin)、ミネラル(英語:mineral)の5大栄養素に加え、昭和50年前後(1970年代)以降、第6の栄養素として重要視されて来たのが食物繊維です。更に 同・60年前後(1980年代)に入り、このフィト・ケミカルが発見されたことで、第7の栄養素として話題を呼びました。
また、去る10月8日(木)の「ノーベル賞」のブログ に、御承知のように、日本人がノーベル医学・生理学賞を受賞したことを言及させて頂きました。受賞者は、自然界にいる微生物が産生する有用な物質(天然物と呼ばれます)を取り出したのです。すなわち、製品化された抗寄生虫薬「イベルメクチン」は、受賞者が発見した土壌細菌が作る抗生物質が基になりました。因みに、そのきっかけは、静岡県のゴルフ場近くの土壌で偶然 見つけた物質でありました。なお、微生物を培養する技術は、味噌や納豆などの生産を通じて研究者の間で職人芸のように培われたそうです。このような天然物化学は、日本の「お家芸」とも言える得意分野とされています。前述の、去る10月8日(木)の「ノーベル賞」のブログ に記させて頂きましたノーベル物理学賞に関しましても、「素粒子物理理論」は日本の「お家芸」とされていますね。因みに、味噌の生産過程につきましては、去る4月8日(水)の「南瓜」のブログ の中段以降に記させて頂きました 。
前者のスルフォラファンは、植物中に存在する天然物であり、後者は、自然界にいる微生物が産生する天然物で御座いますね。天然物化学とは、通常は直接生物が産生する物質のみを扱う有機化学の一分野とされています。近年、製薬手法の主流は天然物化学から化学合成に移って来ているとのことですが、今回の受賞で「お家芸」の復活に弾みがつくかもしれないと言われています。
ときに、昨日、一日のおかず(菜食)は、
まず、タッパー(食品の携帯、そして、保存などに用いるプラスチック製のふた付き密閉容器の通称です。)に詰めた、枝豆です。因みに、去る 昨年の11月6日(木)の「イソフラボン」のブログ で お伝え申し上げましたように、枝豆(大豆)にはイソフラボン(フラボノイド[よく御承知のポリ・フェノールと呼ばれる、より大きな化合物のグループの仲間。]の一種)が含まれています。なお、枝豆(大豆)に含まれています、このイソフラボン(英語:isoflavone)、レシチン(英語:lecithin)、そして、サポニン (英語:saponin)につきましては、前述の 昨日 すなわち 10月10日(土)の「心身一如」のブログ の中段やや上に記させて頂きました。
おまけに、御承知のように、枝豆と大豆、元は同じものですが、未熟な枝豆から更に成熟すると、大豆になります。

枝豆
また、胡瓜、キャベツ、そして、玉葱の白和えです。因みに、胡瓜のことは、去る2月10日(火)の「胡瓜」のブログ に記させて頂きました。しかも、胡瓜の語源につきましては、去る7月2日(木)の「野菜天ぷら」のブログ の中段やや上に記させて頂きました。更に、胡瓜の持つ酵素につきまして、去る7月13日(月)の「トマト煮」のブログ の上段に記させて頂きました。
ならびに、キャベツのことは、去る 昨年の12月20日(土)の「キャベツ」のブログ に記させて頂きました。および、玉葱の調理法につきましては、去る3月25日(水)の「玉葱」のブログ の中段やや下に記させて頂きました。なお、玉葱に含まれるクェルセチン(英語: quercetin)は、前述のイソフラボンと同様にフラボノイドの一種であり、上記のフィト・ケミカルです。強い抗酸化作用があります。クェルセチンはビタミンPの一種と言われることもあります。但し、日本ビタミン学会は、ビタミンPをビタミン様物質として規定しています。つまり、ビタミンPはビタミンではないということを言っています。
生理的なことを記させて頂きますと、血液中の一酸化窒素(化学式:NO)の指令で血管が拡張するのですが、ここに活性酸素が多いと一酸化窒素の働きを妨げ、動脈硬化を引き起こすとされています。ところが、このクェルセチンは、前述のように、活性酸素を中和する抗酸化作用があります。それで、一酸化窒素の正常な働きを促し、血管の柔軟性を保ち、血管をしなやかにしてくれるとされています。そのクェルセチンがあらゆる食材の中でもっとも多く含まれているのが、玉葱とのことです。玉葱のクェルセチンを増やす上では、玉ねぎを約1週間日光に当てておくと、クェルセチンの量が約4倍近く増えるそうです。皮を剝いて干すようにすることがポイント(英語:point)とのことです。クェルセチンは水溶性の成分である為、油で調理し、溶け出さないようにすることが大切ということになりますね。クェルセチンを無駄なく摂取る為には、油で揚げるのが一番とのことです。一酸化窒素に因ませて頂きますと、御承知のように、光化学スモッグ(英語:photochemical smog)や酸性雨の成因に関連しています。その一酸化窒素の生物機能は、昭和60年前後(1980年代)において驚くべき発見とされました。
おまけに、去る 昨年の11月24日(月)の「抗酸化物質」のブログ に、様々な抗酸化物質を記させて頂きました。
そのうえ、白和えのことは、去る2月7日(土)の「白和え」のブログ で記させて頂きました。

白和え
そして、いんげんの黒胡麻和えです。因みに、いんげんには、前述の枝豆の約3倍の食物繊維が含まれているとされています。なお、食物繊維のことは、去る 昨年の11月20日(木)の「切り干し大根」のブロ グ に記させて頂きました。および、去る 昨年の11月17日(月)の「黒胡麻」のブログ でも お伝え申し上げましたように、隠元禅師がいんげん豆をもたらしたとされています。
ならびに、去る 昨年の11月14日(金) のビオチン(ビタミンB7)ブログ や前述の、 去る 昨年の11月17日(月)の「黒胡麻」のブログ の冒頭でも記させて頂きましたが、胡麻の中でも、黒胡麻はいいとされています。更に、黒胡麻には、去る4月1日(水)の「アントシアニン」のブログ に記させて頂きましたように、アントシアニン(英語: anthocyanin)が含まれています。このアントシアニンも、ポリ・フェノール(抗酸化物質)の代表と言われる程 最も種類が多い前述のフラボノイドの仲間であり、上記のフィト・ケミカルです。

いんげんの黒胡麻和え
および、南瓜の団子です。この中から少しです。因みに、南瓜のことは、去る4月16日(木)の「酢漬け」のブログ の中段やや上に記させて頂きました。

南瓜の団子
最後に、昆布と椎茸のダシによります、大根、さつま芋、そして、葱の味噌汁です。因みに、昆布のことは、去る 昨年の10月24日(金)の「健やかに生活をして頂くために」のブログ の中段に記させて頂きました。また、去る3月22日(日)の「わかめ」のブログ の中段に、
「(前略) 昆布やわかめなどの海藻類には、『水溶性食物繊維』であるヘミセルロースが含まれています。(後略)」と記させて頂きまして、食物繊維につきまして お伝えさせて頂きました。更に、食物繊維のことは、前述の、去る11月20日(木)の「切り干し大根(昨日のおかず)」のブログ の中段でも記させて頂きました。
および、さつま芋のことは、前述の、去る 昨年の10月16日(木) の「身土不二」のブログ に記させて頂きました。ならびに、去る2月26日(木)の「舞茸」のブログ の上段に、
「(前略)さつま芋も皮を剝かずに頂きます。こうすれば、さつま芋の皮に含まれているアントシアニンというポリ・フェノール(抗酸化物質)を摂取ることが出来ますね。(後略)」と記させて頂きました。しかも、アントシアニンのことは、前述の、 去る4月1日(水)の「アントシアニン」のブログ に記させて頂きました。なお、抗酸化物質のことは、前述の、去る 昨年の11月24日(月)の「抗酸化物質」のブログ に記させて頂きました。
そして、去る昨年の10月9日(木)の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から大乗へ」のブログ の中段に詳細に記させて頂きましたように、葱にはアリシン(硫化アリル)(英語:allicin)が含まれています。
ところで、昔から言われている味噌汁のことを発展させた話につきましては、去る4月8日(水)の「南瓜」のブログ の中段以降に記させて頂きました。それから、去る7月11日(土)の「日本人の魂の食べ物」のブログ の中段やや下に、
「(前略)去る6月29日(月)の『微笑み』のブログ の中段やや下に、『味噌汁は、日本人の魂の食べ物ですね。』と記させて頂きました。(後略)」と記させて頂きました。そのうえ、去る8月23日(日)の「アスコルビナーゼ」のブログ の下段やや上に、味噌汁である「御御御付」のことにつきまして、
「(前略)『御』が3つも付くのですから、誠に有り難い食べ物ですね。(後略)」と記させて頂きました。

味噌汁
同居している両親は、と以前、訊かれましたので、お伝え申し上げましたが、両親は何でも食べます。
前述の、去る昨年の10月9日(木)の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から大乗へ」のブログ に記させて頂きました過程があり、誠に有り難いことに、母親の理解を得て、菜食にさせて頂いております。
あと、これらのおかずに、玄米御飯で御座います。玄米も、庶民的にスーパー・マーケットで購入して来ます。
御承知のように、玄米の糠には、去る 昨年の11月10日(月)の「らっきょう(昨日のおかず)」のブログ で お伝え申し上げましたように、糖質からエネルギーをつくり出すときに役立つとされているビタミンB1(チアミン)が含まれています。ビタミンB1(チアミン)のことは、去る3月30日(月)の「脳の神経細胞の新生」のブログ の上段から中段に掛けてでも記させて頂きました。
また、らっきょうには、キャベツの約50倍の、前述の「水溶性食物繊維」が含まれています。キャベツのことは、前述の、去る12月20日(土)の「キャベツ」のブログ に記させて頂きました。更に、らっきょうには、ビタミンB1の吸収を助ける、「アリシン(硫化アリル)(英語:allicin)」という成分が多く含まれています。因みに、「アリシン(硫化アリル)」は、葱類に共通して含まれています。玉葱に含まれている、血液をサラサラにする効能があるとされる「アリシン(硫化アリル)」を効果的に摂取るための調理法は、前述の、去る3月25日(水)の「玉葱」のブログ に記させて頂きました。なお、玉葱に多く含まれるフラボノール(英語:flavonol)にも、血液をサラサラにする働きがあるとされています。このフラボノールは、前述のフラボノイド(英語:flavonoid)の一種であり、やはり上記のフィト・ケミカルです。
それから、玄米には、ビタミンE、食物繊維、そして、K(カリウム)が含まれています。因みに、K(カリウム)のことは、去る1月9日(金)の「茄子」のブログ に記させて頂きました。また、玄米のような穀類に含まれている食物繊維は、「不溶性食物繊維」です。前述の「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」のことにつきましては、前述の、去る3月22日(日)の「わかめ」のブログ の中段に記させて頂きました。

玄米御飯
玄米の食べ方につきましては、前述の、去る11月17日(月)の「黒胡麻」のブログ で記させて頂きました。また、玄米の炊き方につきましては、去る11月26日(水)の「蕗」のブログ に記させて頂きました。
(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)
本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)